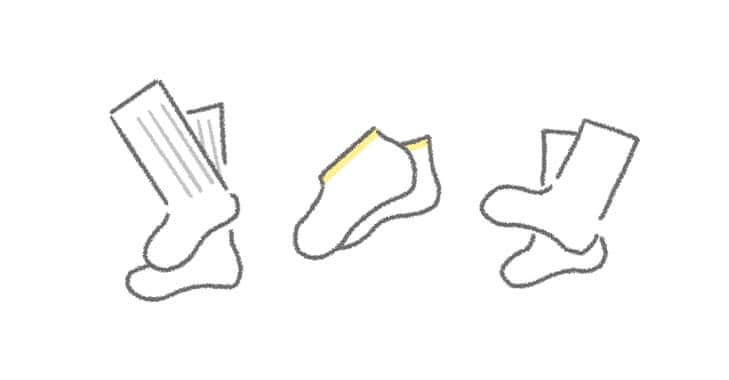地域医療連携室には入院や転院相談に関わる前方支援と、退院に関わる後方支援があります。急性期病棟では特に、患者様の治療や療養が看護の中心となりますが、地域医療連携室では、ご家族も含めた社会的背景や地域との関わりも重要なのです。
今回は地域医療連携室にまつわるあるあるを紹介します。
目次
1.電話対応スキルが身につく
地域医療連携室ではコールセンターさながらに、途切れることなく電話が鳴ります。ご家族やケアマネジャー、施設担当者など、いろいろな方と電話でのやり取りがあります。言葉遣いや声のトーン、伝わりやすい話し方などを常に意識しているため、電話対応のスキルが自然と身につくのです。
2.ビジネスマナーが身につく
他病院や他施設への訪問や名刺交換、メールでのやり取りが頻繁です。訪問した際の座る位置や名刺交換の手順、メールの文章作成など、ビジネスマナーが身につきます。
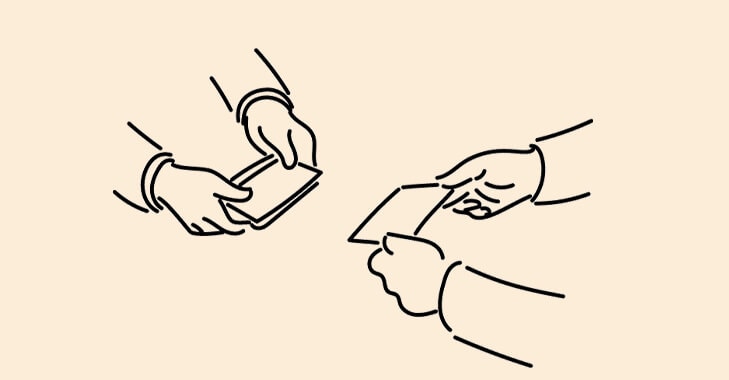
3.患者さんよりご家族の印象が強くなる
後方支援では、退院先や退院後の生活について相談を受けます。ご家族からの連絡が多い場合は、患者さんのお名前を聞くと患者さんより先に、ご家族のイメージが出てくることもしばしば。
4.薬価に敏感になる
老人保健施設(老健)では、内服している薬が高く変更できない場合、受け入れ不可になることがあります。そのため、患者さんが薬価の高い薬を内服していないかとても敏感になるのです。
5.情報シートの重みを感じる
後方支援の際、患者さんのリアルな生活や背景が記載されている情報シートに助けられることが多いのです。担当であるケアマネジャーさんの言葉で記載される「余白部分」の内容は見逃せない貴重な情報です。
6.ADLよりIADLと主張したくなる
退院後のリアルな生活を考えるため「患者さんができること」や「介助内容」について、より細かく具体的に知りたくなります。「一部介助」という表現では、必要な情報は伝わらないものですよ。
7.病棟ではないけれど、多重課題はやっぱりある

多重課題とは、一気にきた複数の依頼や課題にどう対処するかということ。
例えば、Aさんのご家族から相談の電話が入る、またBさんの入所先の施設から看護処置について確認の入電、Cさんのご家族さんが相談したいと来院、病棟からDさんの退院調整の進捗を聞かれる……。これらが一度に起こるため、病棟勤務での「優先順位をつける習慣」は地域連携室でもかなり役立ちます。
まとめ
地域医療連携室では、点滴や採血といった処置がまったくないため、一見、看護師らしさはないかもしれません。
でも実際には、患者さんやご家族、担当ケアマネジャー、施設と退院後の生活について話す際には、看護の視点がとても重要なのです。
看護技術に自信はないけれど、患者さんの退院後の生活を一緒に考えたい、患者さんやご家族の気持ちに寄り添いたい看護師にはおすすめの部署です。
ライタープロフィール
【梅子】ナースLab認定ライター
看護師ライター。社会人から看護師になり11年目。急性期病棟、地域包括ケア病棟、地域医療連携室に勤務。現在は、老人保健施設で勤務しながら、保護犬・保護猫に関する活動を始めるべく準備中。
看護師による看護師のためのwebメディア「ナースの人生アレンジ」