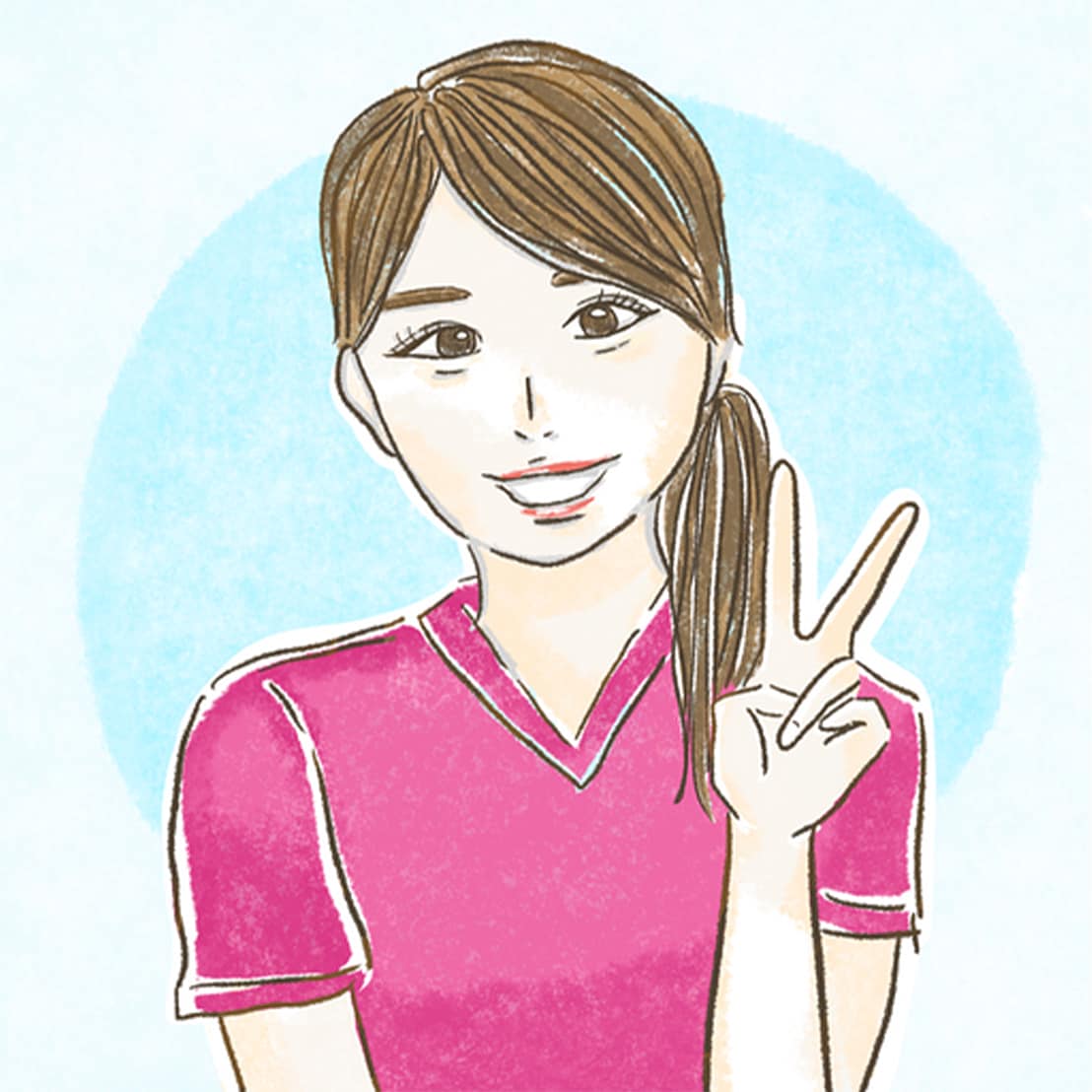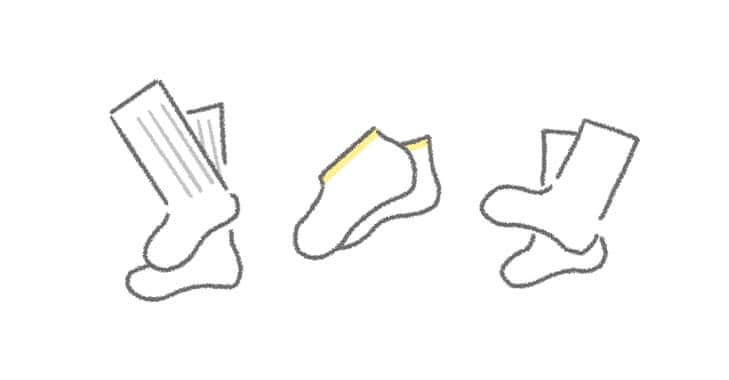患者と接する中で「訴えと実際の症状が一致しない」と感じることがよくあります。患者の言葉をそのまま受け取って判断すると、看護師が想定していたものと違っていた、という経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか。この記事では、患者とのやりとりで感じるコミュニケーションギャップのあるあるについてまとめてみました。
目次
1.痛みの伝え方は患者それぞれ
痛みを尋ねたとき、患者それぞれ表現が異なることがあります。「チクチク」「ズーンとした痛み」など痛みの種類もさまざま。また患者によって痛みの感じ方も異なり「そんなに痛くない」と言っていても実は痛みを強く我慢していることもあるでしょう。反対に薬を飲むほどの痛みではなくても強い痛みを訴える患者もいます。痛みに関しては疼痛スケールなどを活用してできるだけ詳しく感じている痛みの内容を聞き取れると良いですね。
2.「だるい」「しんどい」「気持ち悪い」の意味が患者によって違う
体調を尋ねたときに「だるい」「しんどい」「気持ち悪い」と訴える患者がいます。いずれも同じようなニュアンスの言葉かもしれませんが、症状が発生する時間帯や頻度、持続性など具体的に確認しましょう。表現を具体的にすることで、症状が起こる原因がわかるかもしれません。
3.患者の「大丈夫」は大丈夫じゃないケースが多い

術後や発熱中の患者に体調を聞いたとき「大丈夫」と答える患者は意外と多いはずです。「大丈夫」という言葉を真に受けて観察を怠ると大変なことになります。患者が大丈夫と言ってもしっかり身体状況を把握し本当に問題がないか確認しましょう。我慢強い患者などは多少痛くても「大丈夫」と言ってしまうこともあります。その言葉を鵜呑みにせず、痛いときは無理せず鎮痛剤などの薬に頼っても良いことを伝えましょう。
4.医師と看護師に言うことが違う

看護師には本音を話してくれるのに、医師に自分の希望や考えを言わない患者は少なくありません。「医者には言いにくい」「こんなこと言っても良いのかな?」と遠慮する患者もいます。看護師が患者の思いを汲み取って医師との橋渡しができないわけではありません。しかし、ニュアンスの違いなどを正確に伝えるにも限界があります。結局のところ患者本人が医師に直接思いを伝えるのが一番ではないでしょうか。
5.症状の出現時期が曖昧
患者によっては症状の出現時期を「前から」と表現することが時折ありますが、具体的な時期がわからず困り果てることも。「前から」といってもつい数日前からのケースもあれば、十数年前から続いているケースもあるのです。寛解と出現を繰り返していたという経験もありました。
6.便の量や性状の表現が患者によってさまざま
排便状況を聞いたとき、口頭では食い違うこともしばしば。とくに便の量や性状は患者の言っていることと看護師の思っていることが異なるケースは少なくないでしょう。「結構出たよ」と言われても患者の言う「結構」がどの程度の量なのかはっきりわかりません。具体的に指の本数やバナナなどで表現してもらうと意外に少量だったこともあるでしょう。性状について普段が硬めの場合「まぁまぁ柔らかかった」と言われても、スムーズに出たら柔らかめと表現する患者もいるかもしれません。ブリストルスケールなどを用いてお互いに便の性状を共有するのが確実な方法です。
7.食事量は患者によってさまざま
食事量の確認で「結構食べていますよ」と患者。とはいえ体重が減少傾向であれば、案外食べられていないと判断できます。本人はそこそこの量を食べているつもりでも必要摂取量にまったく到達していないこともあり得るのです。逆に糖尿病などで食事制限のある患者が「食事には気をつけています。あまり食べすぎないようにしています」と言いつつ、間食が多かったり、カロリーの高いものを食べていたりすることも。
8.全然眠れない患者の睡眠状況
「まったく眠れなくて困っています」。こう発言する患者の部屋を夜間巡回すると、案外いびきをかいてぐっすり眠っていることがあります。もしかすると巡回時はたまたま眠っていたのかもしれません。ただ患者によって熟眠感は異なるため、患者の言葉だけを鵜呑みにするのではなく、どのぐらいの頻度で具体的に何時ごろ目覚めたのか情報収集すると良いかもしれません。
9.薬の認識が患者によってさまざま

薬について患者に質問したところ「たくさん薬飲んでいるよ」と返答されたケース。実際に確認してみると、たくさん飲んでいるのはサプリメントのことで、医師から処方されている薬はわずか2種類ほど。また別のケースでは、服薬状況を確認したとき「ちゃんと飲んでいるよ」と言われ、数を確認すると残数がバラバラ。飲み忘れていたり過剰に服薬していたりすることもあったものです。
まとめ
患者によって感じ方や表現方法はさまざまです。患者の普段の感じ方や表現の特徴を知ることは大事かもしれません。経験を積むことで見えてくる部分があるはずです。経験だけでは補いきれないこともあるため、観察と会話の積み重ねが重要なポイントではないでしょうか。
ライタープロフィール
【東 恵理】ナースLab認定ライター
看護師、保健師、介護支援専門員。 国公立大学看護学科卒業後、総合病院にて手術室、外科病棟を経験。その後、小規模多機能型居宅介護施設へ。在職中に介護支援専門員資格取得したことをきっかけに、在宅分野に興味を持ち訪問看護へ転職。一つの働き方に縛られず、フレキシブルな働き方を目指し、ライター業に挑戦。 現在、訪問看護で非常勤として働きながら看護学校非常勤講師や介護士向け研修の講師も務めている。一児の母。
看護師による看護師のためのwebメディア「ナースの人生アレンジ」